学校保健会講演会
2014年12月06日
11月29日に高山市学校保健会主催で
子育てハッピーアドバイスの著者 明橋大二先生を招いての講演会がありました。
我が家にもこの本があり、以前から楽しみにしていた今回の講演、内容もパパにとってタイムリーでした。
会場は満員状態、300名近くが参加したのかな?すごい熱気でした。
でもその反面、悩んでいる保護者(自分も含め)、先生方が多いということかなと思うと
少し複雑・・・
さて、先生の話ですが、さすがいろんなケースに対応しているだけあって、
説得力があるというか、わかりやすいというか言葉一つひとつが胸にストンと落ちていきました。
メモをもとに内容をまとめました。ちょっと抜けているところもありますが、
----------------------------------
以下はメモより
日本の子どもたちの自己肯定感が極端に低い
日本36%
米国89%
中国87%
幼い時の虐待やいじめ親との関わりの薄さ(手のかからない子)
依存と自立の繰り返し
甘えた人が自立する
甘えさせる→〇
・情緒的な要求に応える
・できないことを助ける(信頼感を育てる)
甘やかす→×
・物質的な要求に応える(心のさみしさを物で紛らわす)
・できるのに手を出す
思春期の対応
・反抗は成長の証、反抗したら一安心
具体的な対応
・子どもとの時間をつくる、大切にする
・気持ちを汲んで言葉で返す(言葉育て)
→気持ちの表現が苦手な子が多い、
例)「腹が痛い」などの身体化
「キレる」などの行動化
・できないことより、できていることに注目、
例)60点のテストは、まず6割正解したことをほめる
例)他の子と比較しない、比較対象は以前のその子
・「頑張れ」より「頑張ってるね」
頑張れは、これ以上何をがんばればいいかわからない、苦しめる言葉になる
・「ありがとう」は相手の存在価値を高める。感謝の言葉
子どもにキレてしまうときは、要求ハードルを下げる、肩の力を抜く
さて、肝心の「自己肯定感」はこころの土台として0~3歳までに形成
その上に「しつけ」3~6歳、さらにその上に「勉強」6歳~ となります。
もう手遅れかというとそうではなく
大きくなってからでも「自己肯定感」は形成できる。
気づいたときから始めればよい。
----------------------------------
自己肯定感の低い子どもが大人に成長すれば・・・
精神的に病む大人が増えていることの理由もここにあるのかなと感じました。
それにしてもあっという間の2時間でした。
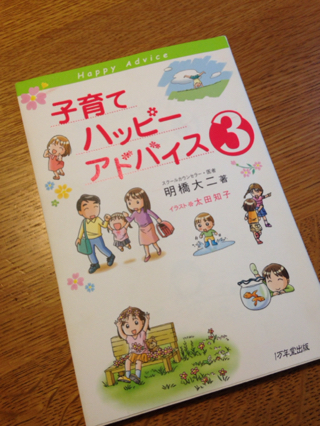
子育てハッピーアドバイスの著者 明橋大二先生を招いての講演会がありました。
我が家にもこの本があり、以前から楽しみにしていた今回の講演、内容もパパにとってタイムリーでした。
会場は満員状態、300名近くが参加したのかな?すごい熱気でした。
でもその反面、悩んでいる保護者(自分も含め)、先生方が多いということかなと思うと
少し複雑・・・

さて、先生の話ですが、さすがいろんなケースに対応しているだけあって、
説得力があるというか、わかりやすいというか言葉一つひとつが胸にストンと落ちていきました。
メモをもとに内容をまとめました。ちょっと抜けているところもありますが、
----------------------------------
以下はメモより
日本の子どもたちの自己肯定感が極端に低い
日本36%
米国89%
中国87%
幼い時の虐待やいじめ親との関わりの薄さ(手のかからない子)
依存と自立の繰り返し
甘えた人が自立する
甘えさせる→〇
・情緒的な要求に応える
・できないことを助ける(信頼感を育てる)
甘やかす→×
・物質的な要求に応える(心のさみしさを物で紛らわす)
・できるのに手を出す
思春期の対応
・反抗は成長の証、反抗したら一安心
具体的な対応
・子どもとの時間をつくる、大切にする
・気持ちを汲んで言葉で返す(言葉育て)
→気持ちの表現が苦手な子が多い、
例)「腹が痛い」などの身体化
「キレる」などの行動化
・できないことより、できていることに注目、
例)60点のテストは、まず6割正解したことをほめる
例)他の子と比較しない、比較対象は以前のその子
・「頑張れ」より「頑張ってるね」
頑張れは、これ以上何をがんばればいいかわからない、苦しめる言葉になる
・「ありがとう」は相手の存在価値を高める。感謝の言葉
子どもにキレてしまうときは、要求ハードルを下げる、肩の力を抜く
さて、肝心の「自己肯定感」はこころの土台として0~3歳までに形成
その上に「しつけ」3~6歳、さらにその上に「勉強」6歳~ となります。
もう手遅れかというとそうではなく
大きくなってからでも「自己肯定感」は形成できる。
気づいたときから始めればよい。

----------------------------------
自己肯定感の低い子どもが大人に成長すれば・・・
精神的に病む大人が増えていることの理由もここにあるのかなと感じました。
それにしてもあっという間の2時間でした。
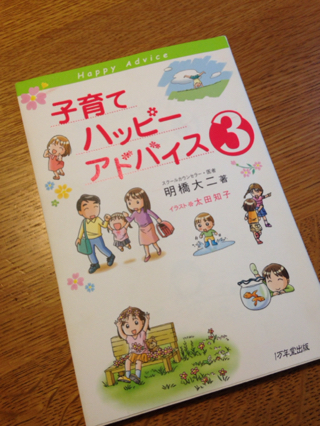
スポンサーリンク
Posted by 花さん at 14:02
